
幼稚園と保育園にピッタリ!人気の出張コンサートおすすめ7選
幼稚園・保育園に訪問してくれる出張コンサートは、子どもたちの五感や感性を育む絶好のチャンス。生の音楽体験を通して、子どもたちの「心に残る一日」を演出できます。ここでは、特に人気のジャンルを7つ厳選し、それぞれのメリット・デメリット、実際の口コミもご紹介します。
和楽器コンサート(和太鼓・三味線・尺八など)

メリット
- 大きな音や振動を体で感じられ、五感に響く体験となる
- 日本の伝統文化に触れられ、教育的価値も高い
- 子どもも手拍子やリズムで参加しやすく、親しみやすい
デメリット
- 音量が大きいため、園の構造によっては音の響きに配慮が必要
- 伝統的な演奏は、一部の子どもにとっては集中力が続かないことも
実際の口コミ
和太鼓と三味線のリズムにノリノリで手拍子していた子が、次の日もずっと真似していました!(東京都・保育園)
-1024x853.jpg)
クラシックコンサート(ピアノ・ヴァイオリンなど)

メリット
- プロの演奏に触れられる貴重な機会
- 音の美しさや空気の振動など、生演奏ならではの魅力がある
- 落ち着いた雰囲気で、聞く姿勢も自然と身につく
デメリット
- 曲によっては子どもには難解で、飽きやすい場合がある
- 派遣コストが高くなりがち
実際の口コミ
子どもたちは45分間静かに聴けていて驚きました。音楽の力を実感しました(大阪府・幼稚園)
体験型コンサート

メリット
- 観るだけでなく、実際に楽器に触れる事が出来る
- 創作や合奏を通じて、協調性や創造力も育てられる
デメリット
- 人数が多い園ではみんなが体験出来ない事も
- 体験のまとまった時間が必要
実際の口コミ
子どもたちが夢中で叩いている姿に感動しました。とても良い経験になりました(千葉県・保育園)

リトミックコンサート

メリット
- 音楽に合わせて体を動かし、子どもが主体的に参加できる
- 協調性やリズム感を自然に育むことができる
デメリット
- 0〜2歳児には体を使った参加が難しい場合もある
- 広いスペースの確保や安全管理が求められる
実際の口コミ
年中さん以上はとても楽しそうに参加していましたが、2歳児は動きについていけず戸惑っていました(神奈川県・保育園)
歌とダンスのリズムコンサート

メリット
- 元気いっぱいに体を動かしながら楽しめる
- 一体感や表現力を育てることができる
- 年長児には特に人気が高いジャンル
デメリット
- 年齢によっては振付やステップについていけないこともある
- 体力の差や個人差による負担も考慮が必要
実際の口コミ
子どもたちはオリジナルソングと振り付けに大喜びでした。帰ってからもずっと歌っていました(埼玉県・幼稚園)
親子参加型ファミリーコンサート

メリット
- 親子で一緒に楽しめる、心温まるイベント
- 保護者も参加することで園全体が盛り上がる
- 子どもが安心して楽しめる雰囲気が生まれる
デメリット
- 保護者の参加人数に応じたスペース確保が必要
- 大人が退屈に感じる内容になることも
実際の口コミ
親子で踊ったり歌ったり、とても楽しい時間を過ごせました(愛知県・保育園)
絵本読み聞かせ×音楽コンサート

メリット
- 音楽と物語の組み合わせで、物語世界に引き込まれる
- 言葉のリズムや表現力を養う効果も期待できる
- 年齢問わず楽しみやすい内容
デメリット
- 絵本のテーマが合わないと子どもが興味を失いやすい
- プロジェクターなどの演出機材が必要になることもある
実際の口コミ
2歳の娘も釘付けになっていました。歌とお話の融合がすばらしかったです(静岡県・幼稚園)
まとめ:ジャンル選びのポイント
- 園児の年齢や発達段階に合わせて選ぶ
- 音量やスペースなど、園の設備に応じた構成が重要
- 教育的な目的か、娯楽・思い出づくり重視かによっても最適なジャンルは異なる
- 保護者の参加有無や季節行事に合わせた企画も効果的
出張コンサートは、日常の保育に彩りを加える素晴らしいイベントです。
子どもたちにとって“本物”の体験となるよう、ジャンル選びからじっくりご検討ください。
ジャンル選びのポイント
文部科学省の「幼稚園教育要領」や、こども家庭庁による「保育所保育指針」では、音楽を含む表現活動は子どもの発達にとって重要な領域とされています。以下に、教育的観点から見たジャンル選びのポイントをまとめます。
1. 音楽は「表現」の領域として位置づけられている
幼児教育において音楽活動は、「表現」の一環として重要視されています。
歌う・演奏する・動くなど、子どもが主体的に関われるプログラムが推奨されます。
おすすめジャンル例:
- リトミック
- 和太鼓体験コンサート
- 親子参加型の音楽あそび
2. 身近な環境での音楽体験が効果的
保育所保育指針では、子どもが「身近な環境で自由に音や音楽に触れられること」が大切だと述べられています。
特別な舞台装置やホールがなくても、保育室や遊戯室で行える内容が望まれます。
おすすめジャンル例:
- 絵本読み聞かせ × 音楽
- アコーディオンや打楽器などの小編成コンサート
- 室内でのシンプルな楽器体験
3. 子どもの主体性・即時反応を促す構成
幼児期の発達では、「即時に反応して表現する」ことが重要とされます。
一方向的な鑑賞ではなく、手拍子・歌・動作などを通じて、参加できる構成が効果的です。
おすすめジャンル例:
- リトミックコンサート
- ダンスや手遊びを取り入れた歌のステージ
- 子ども向け合奏体験
4. 安心できる雰囲気の中で行うこと
保育指針では、子どもが安心して自己を発揮できる環境づくりが大前提とされています。
知らない大人や大きな音に驚きやすい年齢層には、親しみやすい構成や親子同伴の形式が効果的です。
おすすめジャンル例:
- 親子参加型ファミリーコンサート
- 絵本と音楽の融合型ステージ
- 演者が園児と目線を合わせて行う対話型コンサート
5. 協調性や豊かな感性を育てる視点
文部科学省は、幼児期に「協調性」や「豊かな感性・思考力」を育むことを重要な教育目標としています。
集団で歌う・一緒に演奏するなど、他者との関わりが生まれる構成が理想です。
おすすめジャンル例:
- 和楽器コンサート(リズムを合わせる・文化に触れる)
- 歌とダンスの参加型イベント
- 絵本や物語を通じて一体感を得られる音楽劇的演出
教育方針に基づいたジャンル選びまとめ
| 教育的観点(出典:幼稚園教育要領、保育所保育指針) | 対応するコンサートジャンル |
|---|---|
| 表現力・主体性を育む | リトミック、和太鼓体験 |
| 安心できる環境で音楽に触れる | 親子コンサート、室内小編成 |
| 音やリズムへの即時反応を引き出す | ダンス参加型、手遊び歌 |
| 他者と協力・共有しながら楽しむ | 和楽器合奏、絵本+音楽体験 |
幼児教育における音楽・表現活動の指針となる資料一覧
1. 文部科学省「幼稚園教育要領(平成29年告示)」
- 教育目標「表現」領域にて、音・リズム・音楽に関する活動の重要性を記述
https://www.mext.go.jp/content/1384661_3_3.pdf
2. こども家庭庁(旧厚生労働省)「保育所保育指針(平成29年3月)」
- 第2章「保育の内容」にて、乳幼児期の音や動きの体験、表現の重要性を記述
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/eb316dce-fa78-48b4-90cc-da85228387c2/f4758db1/20231013-policies-hoiku-shishin-h30-bunkatsu-1_24.pdf
3. 厚生労働省資料:保育所保育指針解説書(平成30年度版)
- 各年齢に応じた音楽・リズム活動の取り組み例を詳細に解説
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00010450&dataType=0&pageNo=1
4. こども家庭庁:保育実践の質の向上資料
- 環境づくり・参加型活動・安心できる空間についての説明あり
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/36b55701/20231016_policies_hoiku_66.pdf
5. 宮城学院女子大学教育学部「表現領域における音楽活動の指導」
- 音楽活動における子どもの主体性と参加型構成の実践例
https://www.mgu.ac.jp/miyagaku_cms/wp-content/uploads/2021/12/hatsurin_05.pdf
6. 関東短期大学:幼児の表現活動におけるリズムの研究(保育と音楽)
- リトミックや即時反応の意義に関する教育的考察
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00010450&dataType=0&pageNo=1
7. 白藤学園資料:情緒の安定と音楽・絵本活動の関連
- 子どもが安心できる音楽・読み聞かせ空間づくりについて
https://shirafuji.ac.jp/shirafuji_gakuin/wp-content/uploads/2023/04/2021sugiyama2.pdf
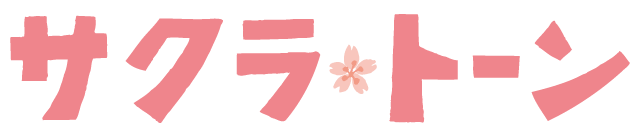

-1-e1691618843209-160x160.jpg)